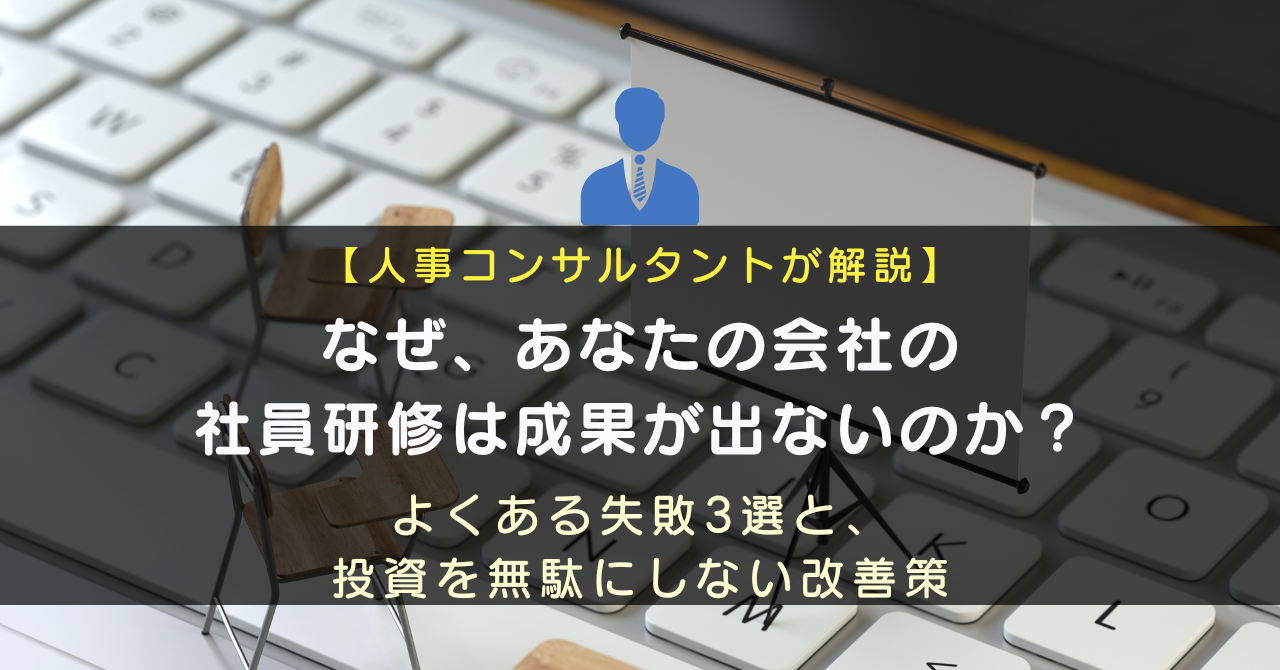研修の成果を阻む「よくある3つの失敗」
「時間とコストをかけて社員研修を実施したのに、現場の行動が何も変わらない…」
「受講後の満足度アンケートの結果は良いが、それが業績に結びついている実感がない」
「研修が、ただの”恒例行事”になってしまっている」
経営者や人事担当者の皆様から、このような切実なご相談をいただくことが少なくありません。
多額の投資を行っているにも関わらず、研修が形骸化してしまうのはなぜでしょうか。
結論から申し上げます。その原因は、研修の内容(コンテンツ)以前の、設計思想と実行プロセスに潜んでいることがほとんどです。
本記事では、数多くの企業の人材育成を支援してきた人事コンサルタントの視点から、研修の成果を阻む「よくある3つの失敗」を構造的に分析し、投資を”成果”に変えるための具体的な改善策を徹底解説します。
なぜ今、戦略的な「人材育成」が不可欠なのか
本題に入る前に、現代における研修の役割の変化について触れておきます。
かつて研修は、決まった知識やスキルを教える「教育」の側面が強いものでした。
しかし、VUCAと呼ばれる変化の激しい時代において、企業が持続的に成長するためには、社員一人ひとりが自ら考え、学び、行動する「自律型人材」であることが不可欠です。
そのため、現代の社員研修は、単発のイベントではなく、企業の経営戦略と連動した、継続的な「人材育成のエコシステム」の一部として設計される必要があります。この視点が欠けていることが、多くの失敗の根源となっているのです。
※VUCA(ブーカ)とは?
Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を組み合わせた言葉で、将来の予測が困難な状況を表します
研修の成果を阻む「よくある3つの失敗」
では、具体的にどのような失敗が研修効果を台無しにしているのでしょうか。
ここでは代表的な3つの構造的欠陥を挙げます。
失敗①:目的が「研修の実施」になっている
最も多く見られるのがこのケースです。
「若手向けにリーダーシップ研修を実施する」「全社でコンプライアンス研修を行う」といったように、「研修をやること自体」が目的化してしまっています。
これでは、人事部門は「研修を実施した」という事実に満足し、受講者は「研修を受けた」というアリバイを得るだけで、具体的な行動変容には繋がりません。
本来の目的は、研修を通じて社員の行動をどう変え、それによって組織にどのような良い影響をもたらすか、であるはずです。
失敗②:研修が「点」で終わり、現場と繋がっていない
研修でどんなに素晴らしい学びや気づきを得ても、日常業務に戻った瞬間にその熱意は急速に失われていきます。
これはロミンガーの法則「70:20:10の法則」でも示される通り、人の成長の7割は「経験」から、2割は「他者からの薫陶(くんとう)」、残りの1割が「研修」からもたらされるためです。
研修という「点」の施策だけで終わらせ、現場での実践(経験)や、上司・同僚からのフィードバック(薫陶)と意図的に結びつけていない場合、研修で得た知識は記憶の彼方に消え、行動として定着することはありません。
失敗③:上司のコミットメントが欠如し、「他人事」になっている
社員の行動変容に最も大きな影響力を持つのは、直属の上司です。
しかし、多くの企業で「研修は人事部がやるもの」という認識が根強く、上司が部下の育成に無関心、あるいは非協力的であるケースが見られます。
研修で「どんどん新しいことに挑戦しよう」と教わっても、現場の上司が「余計なことをするな」という姿勢では、部下は挑戦を諦めてしまいます。
上司を巻き込まずして、研修の成果を現場に根付かせることは不可能と言っても過言ではありません。
研修の投資を「成果」に変えるための3つの改善策
では、これらの失敗を乗り越え、研修を真の成果に繋げるためにはどうすればよいのでしょうか。
3つの具体的な改善策をご提案します。
改善策①:経営課題から逆算した「行動変容ゴール」を設定する
まず、研修の企画段階で「実施すること」をゴールにするのをやめましょう。
スタート地点は「自社の経営課題は何か?」です。
例えば、「新規顧客の開拓が遅れている」という課題があれば、「そのために社員にはどのような行動が必要か?」を考えます(例:既存顧客への深耕だけでなく、異業種交流会への参加や、顧客からの紹介依頼を積極的に行う)。
このように、経営課題→事業目標→必要な行動→研修ゴールという流れで逆算して設計することで、研修は経営に直結する戦略的施策となります。
改善策②:「研修ジャーニー」を設計し、現場での実践を組み込む
研修を単発のイベントで終わらせないために、研修の前後を含めた一連の「学習の旅(ラーニング・ジャーニー)として設計します。
- 研修前(Before):事前課題の提示、上司と部下での1on1面談(研修で何を学びたいか、何を期待するかのすり合わせ)
- 研修中(During):知識習得だけでなく、ケーススタディやロールプレイングなど、実践的なワークを多用
- 研修後(After):研修での学びを現場で実践するための「アクションプラン」を作成・共有。定期的なフォローアップ研修や、実践報告会を実施
このサイクルを回すことで、研修の学びが現場で活かされ、血肉となります。
改善策③:上司を「育成のキーパーソン」として巻き込む
上司を「傍観者」から「育成の主役」へと意識変革させることが不可欠です。
そのための具体的な仕掛けを導入しましょう。
- 上司への事前説明会:研修の目的、内容、そして「上司に期待する役割」を明確に伝えます。
- 部下のアクションプランへのコミット:研修後に部下が立てる実践計画に対し、上司がフィードバックを行い、その実行を支援することを約束させます。
- マネジメント評価への反映:「部下の育成への貢献度」を管理職の人事評価項目に組み込むことで、上司のコミットメントを制度的に担保します。
まとめ:研修は「イベント」ではなく、「組織変革のエンジン」である
成果の出ない研修の多くは、その設計思想に問題を抱えています。
研修を単なるコストやイベントとして捉えるのではなく、企業の未来を創るための戦略的な投資であり、組織変革のエンジンであると位置づけること。
その視点の転換こそが、研修の成果を最大化するための第一歩です。
今回ご紹介した3つの改善策、
- 経営課題から逆算した「行動変容ゴール」を設定する
- 「研修ジャーニー」を設計し、現場での実践を組み込む
- 上司を「育成のキーパーソン」として巻き込む
これらを実践することで、貴社の研修は必ずや、社員の成長と組織の発展に貢献する強力なツールとなるでしょう。
貴社の人材育成戦略、プロの視点で見直しませんか?
研修体系の再構築や、効果的なプログラム設計に関するご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。